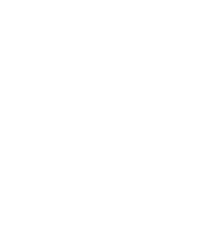再開発で見えてきた、
秋葉原・岩本町エリアの魅力とこれから。


マニアックなイメージが刷新された、東京の新しいオフィス街
かつては日本一の電気街として知られた秋葉原。若者を中心としたカルチャーの発信拠点でもあり、「クールジャパン」の象徴として世界中から注目される文化のメルティング・ポット(人種のるつぼ)として個性を放ってきました。そんな秋葉原に"変化の兆し"が見え始めたのは2000年以降のこと。つくばエクスプレス秋葉原駅の開業を皮切りに、秋葉原駅を境として東西の駅前エリアが再開発され、超高層オフィスビルや大型複合施設が相次いで開業。現在の秋葉原は、かつて漂っていたマニアックなイメージが刷新され、さまざまな情報が集い、次世代のビジネスを創造してゆく熱気とエネルギーに満ちたビジネス街に変貌しつつあります。
また、秋葉原の変化に呼応するように変わりつつあるのが、神田川を挟んだ南側に位置する岩本町エリアです。10数年前までここは、専門性の高い会社が密集した下町風情が溢れるエリアでしたが、現在の街並みは大きく変わり、「交通利便性」というメリットを強みとした注目のビジネスエリアになっています。


- 2024.11.28:エリア特集 #39 再開発で生まれる未来を彩る新たなシンボル
- 2024.09.24:エリア特集 #38 100年に1度の渋谷駅周辺再開発プロジェクトがいよいよ最終段階へ!
- 2024.07.30:エリア特集 #37 高機能オフィスビルへの建て替えを促して「選ばれる街」に
- 2024.05.28:エリア特集 #36 リニア時代に備え、強い経済力と持続可能な街づくりが進む
- 2024.03.25:エリア特集 #35 大阪の都市機能が頂点に!主要ビジネスエリアの再開発
- 2023.06.27:エリア特集 #34 国内外から人とビジネスを呼び込み"超成長"を目指す福岡市
- 2023.02.27:エリア特集 #33 再開発で都心部を整備して集約型都市構造の実現を目指す 広島市
- 2022.11.28:エリア特集 #32 新しい文化が融合したエネルギッシュなビジネスタウンへ 川崎市
- 2022.08.25:エリア特集 #31 東京第3の副都心・池袋 急ピッチの再開発で街が変わる!
- 2022.05.24:エリア特集 #30 大規模再開発で 新たな街に生まれ変わる 浜松町・竹芝エリア
- 2022.02.24:エリア特集 #29 始動!国内屈指の複合再開発 品川開発プロジェクト 品川・田町
- 2021.12.17:エリア特集 #28 新幹線の札幌延伸を睨み 大規模な再開発ラッシュに沸く 札幌市
- 2021.09.21:エリア特集 #27 再開発で見えてきた、 秋葉原・岩本町エリアの魅力とこれから。
- 2021.06.28:エリア特集 #26 国際的ビジネス拠点に相応しい基盤整備とオフィス街周辺の街づくりが進捗 虎ノ門エリア
- 2021.01.26:エリア特集 #25 将来の利便性が期待でき、 これからの時代に相応しい街づくり 仙台市
- 2020.09.02:エリア特集 #24 開港以来、進化を止めないまち 横浜市
- 2020.02.27:エリア特集 #23 街の変化と人口増加が止まらない! 最強地方都市 福岡
- 2019.12.04:エリア特集 #22 都市機能をバージョンアップ 活気に満ちたビジネスエリアに 静岡市
- 2019.08.28:エリア特集 #21 魅力は職住近接!劇的な変貌を遂げる 千葉駅周辺エリア
- 2019.06.03:エリア特集 #20 消費の街からビジネスエリアに 進化と変貌を続ける副都心・新宿
- 2019.02.25:エリア特集 #19 三宮が変わる! 動き出した国際都市・神戸
- 2018.11.29:エリア特集 #18 若者の聖地から、大人のビジネスエリアへ 東京渋谷区
- 2018.09.12:エリア特集 #17 再開発とリニア中央新幹線で大注目! 品川駅周辺エリア
- 2018.05.30:エリア特集 #16 さいたま市随一のビジネスエリアでキーステーション さいたま市大宮区
- 2018.02.23:エリア特集 #15 基地の街から先進的なビジネスエリアへ 東京都立川市
- 2017.08.25:エリア特集 #14 日本経済の一翼を担う大阪市《後編》
- 2017.05.29:エリア特集 #13 日本経済の一翼を担う大阪市《前編》
- 2017.02.16:エリア特集 #12 成熟度を増していく名古屋のいま、そしてこれから
- 2016.10.30:エリア特集 #11 真のコンパクトシティを実現する大分市
- 2016.06.20:エリア特集 #10 福岡特集:地方都市からアジアの経済都市へ
- 2016.04.01:エリア特集 #9 本社機能移転を計画する企業を後押し/三重
- 2015.12.01:エリア特集 #8 函館を中心とした新商圏誕生か/北海道函館
- 2015.07.30:エリア特集 #7 那覇新都心と県のIT企業誘致/沖縄県那覇
- 2015.04.17:エリア特集 #6 コンパクトシティ富山の未来計画/富山県富山
- 2014.11.28:エリア特集 #5 ニューフードバレー構想/新潟県新潟
- 2014.06.30:エリア特集 #4 西日本エリアの経済中枢都市/広島県広島
- 2013.12.17:エリア特集 #3 北海道経済を刺激する新たな流通拠点/北海道石狩
- 2013.08.09:エリア特集 #2 いま熊本経済は「くまモン」効果で活力向上中/熊本県
- 2013.03.25:エリア特集 #1 R仙台駅周辺で注目される街の再開発とは/宮城県
過去の記事
ビジネスマンのメンタルヘルス
〈28〉 愚痴るというカタルシス 「真剣だと知恵が出る。中途半端だと... 2025.03.25更新 駅チカビル
〈21〉 東北地方の中心都市・仙台 ビジネスを育む新たな躍動拠点へ 現在、仙台駅周辺は「せんだい都心再構築プロジェクト」... 2025.03.25更新 Officeオブジェクション
〈23〉 オフィスに固定電話は必要か? 2022年に総務省がおこなった「通信利用動向調査」で... 2025.03.25更新 その道のプロに聞く
〈1〉 企業のサイバーセキュリティ ITジャーナリスト 三上 洋さん パソコンにランサムウェアを感染させて身代金を要求する... 2025.02.28更新 ワークスタイル・ラボ
〈19〉 2025年の働き方のトレンド『心理的安全性』 連日のように「ガバナンス」という言葉を... 2025.02.25更新 リアル・ビジネス
英会話〈33〉
〈33〉 about 5minutes late 相手を待たせてしまう場合 約束の時間すこし前に到着するはずだったのに... 2025.01.28更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈27〉 ネガティブな感情は悪いものではない ストレスを感じやすい現代社会では、誰もが... 2025.01.28更新 リアル・ビジネス
英会話〈32〉
〈32〉 We're going to ドナルド・トランプの勝利宣言 2024年11月5日に投票がおこなわれた... 2024.12.25更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈26〉 苦手な人との付き合い方 職場や取引先に苦手な人がいる。けれど... 2024.12.24更新 オフィス探訪
〈23〉 新オフィスは、ワンフロアに500席確保が絶対条件 株式会社エイチ・アイ・エスのオフィス 株式会社エイチ・アイ・エス(以後HIS)は1980年に... 2024.12.24更新 エリア特集
〈39〉 再開発で生まれる未来を彩る新たなシンボル 江戸時代から商業や文化の中心地として... 2024.11.28更新 若手のための
“自己キャリア”〈24〉
〈24〉 会計リテラシー 会計という言葉には「専門的な... 2024.11.26更新
〈28〉 愚痴るというカタルシス 「真剣だと知恵が出る。中途半端だと... 2025.03.25更新 駅チカビル
〈21〉 東北地方の中心都市・仙台 ビジネスを育む新たな躍動拠点へ 現在、仙台駅周辺は「せんだい都心再構築プロジェクト」... 2025.03.25更新 Officeオブジェクション
〈23〉 オフィスに固定電話は必要か? 2022年に総務省がおこなった「通信利用動向調査」で... 2025.03.25更新 その道のプロに聞く
〈1〉 企業のサイバーセキュリティ ITジャーナリスト 三上 洋さん パソコンにランサムウェアを感染させて身代金を要求する... 2025.02.28更新 ワークスタイル・ラボ
〈19〉 2025年の働き方のトレンド『心理的安全性』 連日のように「ガバナンス」という言葉を... 2025.02.25更新 リアル・ビジネス
英会話〈33〉
〈33〉 about 5minutes late 相手を待たせてしまう場合 約束の時間すこし前に到着するはずだったのに... 2025.01.28更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈27〉 ネガティブな感情は悪いものではない ストレスを感じやすい現代社会では、誰もが... 2025.01.28更新 リアル・ビジネス
英会話〈32〉
〈32〉 We're going to ドナルド・トランプの勝利宣言 2024年11月5日に投票がおこなわれた... 2024.12.25更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈26〉 苦手な人との付き合い方 職場や取引先に苦手な人がいる。けれど... 2024.12.24更新 オフィス探訪
〈23〉 新オフィスは、ワンフロアに500席確保が絶対条件 株式会社エイチ・アイ・エスのオフィス 株式会社エイチ・アイ・エス(以後HIS)は1980年に... 2024.12.24更新 エリア特集
〈39〉 再開発で生まれる未来を彩る新たなシンボル 江戸時代から商業や文化の中心地として... 2024.11.28更新 若手のための
“自己キャリア”〈24〉
〈24〉 会計リテラシー 会計という言葉には「専門的な... 2024.11.26更新