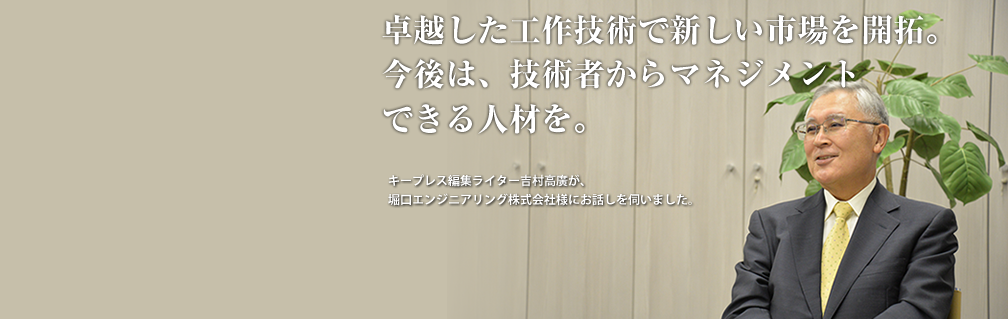堀口エンジニアリング株式会社は、創業以来68年、一貫して工作機械の製造とメンテナンスを行っている中堅企業だ。対象とするマーケットは、自動車、建設機械、船舶、航空機、工場設備のプラントまでと多岐にわたる。身を置く業界をひと言で括るなら、広い意味での修理・製造業。規模の大小はあるものの競合がひしめく業界と言えるだろう。そうした中で「堀口エンジニアリングの強みは何か」といえば、小企業と比べれば高品質の仕事が提供できること、大企業と比較するなら低価格かつフットワーク良く仕事ができるところにある。自社のポジションについて堀口昇治社長は次のように話す。
「困った時の堀口エンジニアリングということになるでしょうか。そうした会社の在り方は昔から変わりません。何かが壊れて早急に直さなければならない。しかもそれが、特殊な技術を必要とするものである場合にご相談いただくちょうどいい会社なのです」と。加えて堀口エンジニアリングには、工作機械を設計できる技術者がいることも大きなアドバンテージである。規模の小さな会社では設計者まで抱えているところはほとんどなく、大規模の会社では仕上がりにスピードを求めることが難しい。まさしく堀口社長が言う通り「ちょうどいい」スタンスで68年間も成長し続けてきた会社なのだ。
困った時の堀口エンジニアリング
チャレンジ・スピリッツで新市場を開拓
堀口エンジニアリングの歴史をさかのぼると、昭和22年に現堀口社長のお父様が、自動車部品の機械加工と溶接加工を行う『堀口内燃機工業所』を創業。ここからその歴史はスタートした。当時は戦後の日本の復興がこれから始まるという時代。当然ながら一般的な自家用車は普及しておらず産業用に使用されるバスやトラックのエンジンや足回りの修理を行っていた。
その後、昭和30年代に入り日本はモータリゼーション時代に突入し、その波に乗って堀口内燃機は大きく発展を遂げることとなる。さらに10年後の昭和40年に調布工場を新設し、特殊機械ならびに超大型クランクシャフト研磨機を導入。船舶関係の分野にも領域を拡大する。そして昭和43年には蒲田工場を新設。航空機整備機材並び特殊車両分野で完全受注生産体制を確立。この頃に今の堀口エンジニアリングのボトムが築かれることとなる。そこには、技術者たちの並々ならぬチャレンジ・スピリッツがあったはず、と堀口氏は推測する。
その後、昭和30年代に入り日本はモータリゼーション時代に突入し、その波に乗って堀口内燃機は大きく発展を遂げることとなる。さらに10年後の昭和40年に調布工場を新設し、特殊機械ならびに超大型クランクシャフト研磨機を導入。船舶関係の分野にも領域を拡大する。そして昭和43年には蒲田工場を新設。航空機整備機材並び特殊車両分野で完全受注生産体制を確立。この頃に今の堀口エンジニアリングのボトムが築かれることとなる。そこには、技術者たちの並々ならぬチャレンジ・スピリッツがあったはず、と堀口氏は推測する。

▲大型衛星横転装置

▲航空機用車椅子昇降機
航空機から船舶分野への進出
「船舶分野への進出。これはエンジンにしても足回り(船舶の場合はスクリュー)についても、それまで自動車で培ってきた技術を転用することができました。しかしながら、船の場合は甲板の上にさまざまな装備品や設備品が設置されますが、そうしたものの製造も調布工場の新設と共に開始しました。これらについては全く新しい技術が必要とされましたが、今までの技術を応用しつつ、試行錯誤繰り返しながら何とかリクエストに応え続けて信頼を獲得して行ったわけです。こうした未知の分野や新しい技術へのチャレンジが、その後の航空機やロケット産業にも進出する原動力となったことは間違いないでしょう」。

▲アルミ船ウォータージェット取付穴、及び面加工

▲小型巡視船 取付台座面加工
職人的な技術と経営スキルは違う
そうした会社を堀口氏が引き継いだのは平成16年のこと。それまで堀口氏は日本最大の広告代理店に勤務するサラリーマンであった。子どもの頃からお父様の仕事は近くで見ていたとはいえ、全くの畑違いである。
「小さな頃から見ていたからこそ跡を継ぐのが嫌だったんです(笑)。父が亡くなり、直後は父の弟である叔父が継いだのですが、年齢などの問題もあっていよいよやれなくなったといった時、これはもう自分が継ぐしかないなと覚悟を決めた次第です」。
堀口氏が転職を決心したのは幾つかの理由があったと言う。まず、第一には、お父様が苦労して立ち上げた会社を「堀口」の名前で継続させることが、ご存命中のお父様にできなかった親孝行になると考えたこと。そしてもう一つは、当時在籍していた従業員の中には会社経営のスキルを持った人材が存在しなかったという2点である。 「私どもの会社には、父の時代から会社を支えてくださった優れた技術を持つ職人さんが数多くいます。しかしながら、職人的な技術を持っていることと経営は違います。もちろん、職人的な技術を持ちながら経営センスもあわせ持つ人も中にはいるでしょうが、中小企業ではそうした人材を育てる機会はなかなかありません。むしろそうした方々にしても、大政奉還とでも言いましょうか、創業者の長男が経営をやるというのが一番収まりがいいと思っている方が多いのです」。
堀口氏が転職を決心したのは幾つかの理由があったと言う。まず、第一には、お父様が苦労して立ち上げた会社を「堀口」の名前で継続させることが、ご存命中のお父様にできなかった親孝行になると考えたこと。そしてもう一つは、当時在籍していた従業員の中には会社経営のスキルを持った人材が存在しなかったという2点である。 「私どもの会社には、父の時代から会社を支えてくださった優れた技術を持つ職人さんが数多くいます。しかしながら、職人的な技術を持っていることと経営は違います。もちろん、職人的な技術を持ちながら経営センスもあわせ持つ人も中にはいるでしょうが、中小企業ではそうした人材を育てる機会はなかなかありません。むしろそうした方々にしても、大政奉還とでも言いましょうか、創業者の長男が経営をやるというのが一番収まりがいいと思っている方が多いのです」。
社員を知ることに費やした2年間
とはいえ、新しい社長がイスに座った途端、意見の相違を主張する社員が出てくることは、会社の規模を問わず概ねある。ところが堀口エンジニアリングではそのような声が聞こえてくることはなかったと言う。その理由は、その頃会社が若手社員を中心に、新たな変革期にさしかかっていたため、新しい経営に対する期待感があったのではないかと堀口氏は推測する。
「それまでは確かに、特殊分野の技術力やフットワークの良さでお客さまから信頼を得て来ましたが、これからは積極的に新規事業への足掛かりをつくって行かないとまずいだろうという認識を私は持っていました。若手の社員たちも同じようなことを考えていたと思います。そうしたタイミングで私が舵取りを任せられましたので、肩に力を入れてぐいぐい引っ張って行くのではなく、ソフトランディングしながら、社員の方たちと信頼関係が築けたところで新しい手を打とうと考えていたわけです」。
ここが堀口氏の経営センスである。堀口氏は社長就任後、2年ほどは現場に口出しすることもなく、社員たちを見守り「人を知る」ことに徹した。ともすれば、いきなり大胆な改革案を打ち出して、旧態依然とした経営体制にメスを入れようとする向きも少なくない。そこを、若手の意見を片耳で聞きながらも、あえて時間をかけて社員の気持ちを把握しつつ、同時に、次なる堀口エンジニアリングのロードマップをつくっていくというのは相当な我慢が必要だ。ただそれができた背景には、これまでの堀口エンジニアリングを支えてきたベテラン技術者たちへの敬意の気持ちがあり、同時にそれは、今後も必ずや必要となる大事なスキルであることを知っていたからに他ならない。
「それまでは確かに、特殊分野の技術力やフットワークの良さでお客さまから信頼を得て来ましたが、これからは積極的に新規事業への足掛かりをつくって行かないとまずいだろうという認識を私は持っていました。若手の社員たちも同じようなことを考えていたと思います。そうしたタイミングで私が舵取りを任せられましたので、肩に力を入れてぐいぐい引っ張って行くのではなく、ソフトランディングしながら、社員の方たちと信頼関係が築けたところで新しい手を打とうと考えていたわけです」。
ここが堀口氏の経営センスである。堀口氏は社長就任後、2年ほどは現場に口出しすることもなく、社員たちを見守り「人を知る」ことに徹した。ともすれば、いきなり大胆な改革案を打ち出して、旧態依然とした経営体制にメスを入れようとする向きも少なくない。そこを、若手の意見を片耳で聞きながらも、あえて時間をかけて社員の気持ちを把握しつつ、同時に、次なる堀口エンジニアリングのロードマップをつくっていくというのは相当な我慢が必要だ。ただそれができた背景には、これまでの堀口エンジニアリングを支えてきたベテラン技術者たちへの敬意の気持ちがあり、同時にそれは、今後も必ずや必要となる大事なスキルであることを知っていたからに他ならない。

大企業のやり方では中小企業は変わらない
就任2年にして初めて打って出た策が『堀口エンジニアリング第二創業期』。新旧社員の相互理解を意識した宣言だ。その頃抱えていた課題は、職場におけるコミュニケーション不足。チームワークで仕事をするという気持ちの欠落だった。機械加工の仕事というのは、基本的には、朝出社してきてから帰るまで自分が担当する機械と向き合って、人とのコミュニケーションをあまり求められない仕事である。そこで堀口氏が手がけたのが、ベテラン・若手各々のリーダークラスと外部の専門家を交えて行った新しい企業理念の策定とその共有だ。しかしながら、理念というのは時として念仏になりかねない。もっとドラスティックな策が必要ではないか...。
「そうは思いません。大企業と中小企業の一番の違いは、大企業には人もたくさんいますし、部門もたくさんあるので社員同士が常に顔を突き合わせているという状況はありません。また、同じような技能を持った人は他の部署に必ずいて代わりはいくらでもいます。ところが中小企業はそうはいきません。一人ひとりが大切な財産であり、その人の代わりはいません。そうなると、何かいさかいが起こっても代わりの人を配置させることもできませんし、その状況に我慢しながらその人に頑張ってもらうしかない。このあたりを上手く回していくことが中小企業のマネジメントの難しさです。そのためには、自分たちの目的や、在るべき姿を明確にして、それを一人ひとりが共有して職場を常に活性化させることが大事です」。
会社を変えようと思うなら、大企業に通用する手法と、中小企業に通用する手法は違うことをしっかり認識しなくてはならないと堀口氏は話す。そして今後は、そうした中から技術力の向上のみならず、ミドルマネジメント、あるいはその上のマネジメントができるような若い力を育てて行く必要があると言う。
「そうは思いません。大企業と中小企業の一番の違いは、大企業には人もたくさんいますし、部門もたくさんあるので社員同士が常に顔を突き合わせているという状況はありません。また、同じような技能を持った人は他の部署に必ずいて代わりはいくらでもいます。ところが中小企業はそうはいきません。一人ひとりが大切な財産であり、その人の代わりはいません。そうなると、何かいさかいが起こっても代わりの人を配置させることもできませんし、その状況に我慢しながらその人に頑張ってもらうしかない。このあたりを上手く回していくことが中小企業のマネジメントの難しさです。そのためには、自分たちの目的や、在るべき姿を明確にして、それを一人ひとりが共有して職場を常に活性化させることが大事です」。
会社を変えようと思うなら、大企業に通用する手法と、中小企業に通用する手法は違うことをしっかり認識しなくてはならないと堀口氏は話す。そして今後は、そうした中から技術力の向上のみならず、ミドルマネジメント、あるいはその上のマネジメントができるような若い力を育てて行く必要があると言う。

社員の幸せは一人ひとり自己研鑽から
経営者が考えるべきは、会社の存続と社員の幸せに他ならない。しかしながら、社員が幸せであるためには、一人ひとりが力をつけて自信を持って働き、利益を生み出せるようでなくてはならない。そこで望まれるのが「この会社で働き続けたい、力をつけたい」と思えるような環境や仕組みの提供だ。「私自身は、さまざまな機会を通じて社員たちと話しをするようにしていますし、会社としても、自己研鑽をして自信をつけてもらうために、機械加工の国家資格取得をバックアップしています。機械加工の資格試験は、筆記に加えて実技もあるのですが、勤務時間内に実際の機械をいじらせて技術を学ぶ機会を設けています。これが若手のモチベーション向上につながっています。二級を取れば、次は一級を狙いたいという社員がぞくぞくと出ていますし、まだ資格を持っていない人には先輩たちが手厚く指導するなどして資格取得に向けて日々自己研鑽しています。まさしくこうした社員同士の関わりこそが、課題であったコミュニケーション不足の解消にもつながっていくのです」。
経営トップが積極的に社員に歩み寄っていくこと。飲み会を開いて無礼講で話し合うこと。どれも大事なコミュニケーション対策だが、最も肝心なのは、社員が職場の中で「もっと成長したい」と思い、主体的に人や仕事と関わりを持つことに他ならない。堀口エンジニアリングには今、そうした気風が満ちている。


- 2023.05.22:企業見聞 #31 AIがデータを解析して好意度を予測し、消費者に刺さるパッケージデザインを制作する。
- 2022.12.22:企業見聞 #30 脱・下請けで100億円企業を目指す、株式会社リゲッタの紆余曲折。
- 2022.07.27:企業見聞 #29 飽和状態の都心型歯科クリニック 生き残りのカギは既存患者の満足度向上
- 2022.03.22:企業見聞 #28 『世の中から卒業をなくす』をミッションに、社会のリテラシー向上に尽力する。
- 2021.11.26:企業見聞 #27 100人に1人に刺さる製品づくりで、 クラフトビール業界を牽引する
- 2021.07.27:企業見聞 #26 成長のキーワードは新陳代謝の促進。 価値の二極化に上質をもって応えてゆく
- 2021.03.24:企業見聞 #25 激変するライブ・エンタテイメント市場に、 新しい価値を創出し続ける。
- 2020.12.21:企業見聞 #24 伴走型コンサルティングで、 サスティナビリティをビジネスにする。
- 2020.06.22:企業見聞 #23 ショッピングセンターの草分けとして、 明るい未来を展望する。
- 2020.02.10:企業見聞 #22 東京五輪後は"求人広告"の新世紀 そこで、夢を語れる企業でありたい
- 2019.10.28:企業見聞 #21 半導体から宇宙開発事業 産業を支えるエネルギーの担い手
- 2019.06.20:企業見聞 #20 白樺湖に、世界に通用するリゾートをつくる。
- 2019.01.24:企業見聞 #19 理屈抜きに旨い酒造りでブームの再来を。銘酒・賀茂泉の成長戦略
- 2018.11.21:企業見聞 #18 頑張るだけでは現状維持すら困難。人も企業も"殻を破って"成長する。
- 2018.07.23:企業見聞 #17 マーケティングとアイディアで業界のリーディングカンパニーへ
- 2018.03.20:企業見聞 #16 百花繚乱の"東京土産"市場で トップシェアを目指す
- 2017.10.25:企業見聞 #15 グローバル戦略で、 世界の麺市場を席巻する
- 2017.07.26:企業見聞 #14 ペット関連市場で業界資産の拡大をも視野にイノベーションを
- 2017.04.24:企業見聞 #13 スイーツブームを支えた製菓パッケージのトップランナーとして
- 2016.11.22:企業見聞 #12 日本品質を担保する 『技術商社』として
- 2016.04.26:企業見聞 #11 ニッチな事業領域を深掘りし、顧客から信頼を勝ち取る
- 2015.11.04:企業見聞 #10 卓越した工作技術で新しい市場を開拓
- 2015.06.09:企業見聞 #9 印刷以外の付加価値提供を行いながら、win×winの関係を築いていく。
- 2014.12.26:企業見聞 #8 セルフメディケーション時代の一翼を担う
- 2014.09.22:企業見聞 #7 今に満足することなくチャレンジする
- 2014.07.14:企業見聞 #6 お客様と一緒に歓喜できる店づくりを。
- 2014.04.28:企業見聞 #5 マーケティングの目的は、ユーザーとの距離を縮めること。
- 2013.11.28:企業見聞 #4 歴史だけでは勝ち目はない。差別化は、最先端のツールによって。
- 2013.09.26:企業見聞 #3 経営理念の共有で、100年企業を目指す。
- 2013.06.25:企業見聞 #2 販売最前線の課題を、利他の心で解決する。
- 2013.03.25:企業見聞 #1 プロの意識の徹底で、福島から世界を目指す
過去の記事
駅チカビル
〈30〉 都市機能の高度化が加速する 東京屈指の超進化型ビジネスエリア 京橋・日本橋から八重洲にかけての一帯は、近年とりわけ... 2025.12.23更新 ワークスタイル・ラボ
〈23〉 ワークスタイルが変わる! 2026年はミドル世代のキャリア投資元年 コロナ禍により働き方が大きく揺れ動いた2020年代前半.. 2025.12.23更新 オフィス探訪
〈28〉 柔軟な働き方とコミュニケーションを両立 株式会社BSCのオフィス 株式会社BSCは、1989年に設立された独立系のシステム開発企業です... 2025.12.23更新 Officeオブジェクション
〈27〉 AI時代に"オフィスの必然性"を見つめ直す AI の進化は知的業務の補助を超え、判断の... 2025.12.23更新 オフィス探訪
〈27〉 壁のないオフィスが、壁のない組織をつくる QUADRAC株式会社のオフィス QUADRAC株式会社は、公共交通向け決済・認証プラットフォームを... 2025.12.01更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈32〉 Z世代の気持ちを読み取るヒント 価値観やものの考え方は、時代の移り変わり... 2025.11.25更新 若手のための
“自己キャリア”〈26〉
〈26〉 声の大きな人は出世する? ビジネスキャリアを左右する話しかた 「声の... 2025.11.25更新 Officeオブジェクション
〈26〉 非固定化するオフィスに残る"固定"とは 企業における働き方の革新は、もはや制度の... 2025.10.28更新 ワークスタイル・ラボ
〈22〉 ワークライフバランス再考 日本を変える、会社を変える、これからの働き方 「ワークライフバランスを捨てます」。何かと.. 2025.10.28更新 オフィス探訪
〈26〉 100年の歩みを、未来の原動力につなげる 東洋電信電話工業株式会社のオフィス 今年、創業100周年を迎えた東洋電信電話工業株式会社(TDD)は... 2025.10.28更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈31〉 感情を逆なでせず、若手世代を味方にする① 入社したばかりの新入社員が、1年を待たずに... 2025.09.26更新 オフィス探訪
〈25〉 好立地を生かした共創の場へ 株式会社アイシン東京事務所 株式会社アイシンは、1965年の創立以来、モビリティの進化とともに... 2025.09.26更新
〈30〉 都市機能の高度化が加速する 東京屈指の超進化型ビジネスエリア 京橋・日本橋から八重洲にかけての一帯は、近年とりわけ... 2025.12.23更新 ワークスタイル・ラボ
〈23〉 ワークスタイルが変わる! 2026年はミドル世代のキャリア投資元年 コロナ禍により働き方が大きく揺れ動いた2020年代前半.. 2025.12.23更新 オフィス探訪
〈28〉 柔軟な働き方とコミュニケーションを両立 株式会社BSCのオフィス 株式会社BSCは、1989年に設立された独立系のシステム開発企業です... 2025.12.23更新 Officeオブジェクション
〈27〉 AI時代に"オフィスの必然性"を見つめ直す AI の進化は知的業務の補助を超え、判断の... 2025.12.23更新 オフィス探訪
〈27〉 壁のないオフィスが、壁のない組織をつくる QUADRAC株式会社のオフィス QUADRAC株式会社は、公共交通向け決済・認証プラットフォームを... 2025.12.01更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈32〉 Z世代の気持ちを読み取るヒント 価値観やものの考え方は、時代の移り変わり... 2025.11.25更新 若手のための
“自己キャリア”〈26〉
〈26〉 声の大きな人は出世する? ビジネスキャリアを左右する話しかた 「声の... 2025.11.25更新 Officeオブジェクション
〈26〉 非固定化するオフィスに残る"固定"とは 企業における働き方の革新は、もはや制度の... 2025.10.28更新 ワークスタイル・ラボ
〈22〉 ワークライフバランス再考 日本を変える、会社を変える、これからの働き方 「ワークライフバランスを捨てます」。何かと.. 2025.10.28更新 オフィス探訪
〈26〉 100年の歩みを、未来の原動力につなげる 東洋電信電話工業株式会社のオフィス 今年、創業100周年を迎えた東洋電信電話工業株式会社(TDD)は... 2025.10.28更新 ビジネスマンのメンタルヘルス
〈31〉 感情を逆なでせず、若手世代を味方にする① 入社したばかりの新入社員が、1年を待たずに... 2025.09.26更新 オフィス探訪
〈25〉 好立地を生かした共創の場へ 株式会社アイシン東京事務所 株式会社アイシンは、1965年の創立以来、モビリティの進化とともに... 2025.09.26更新